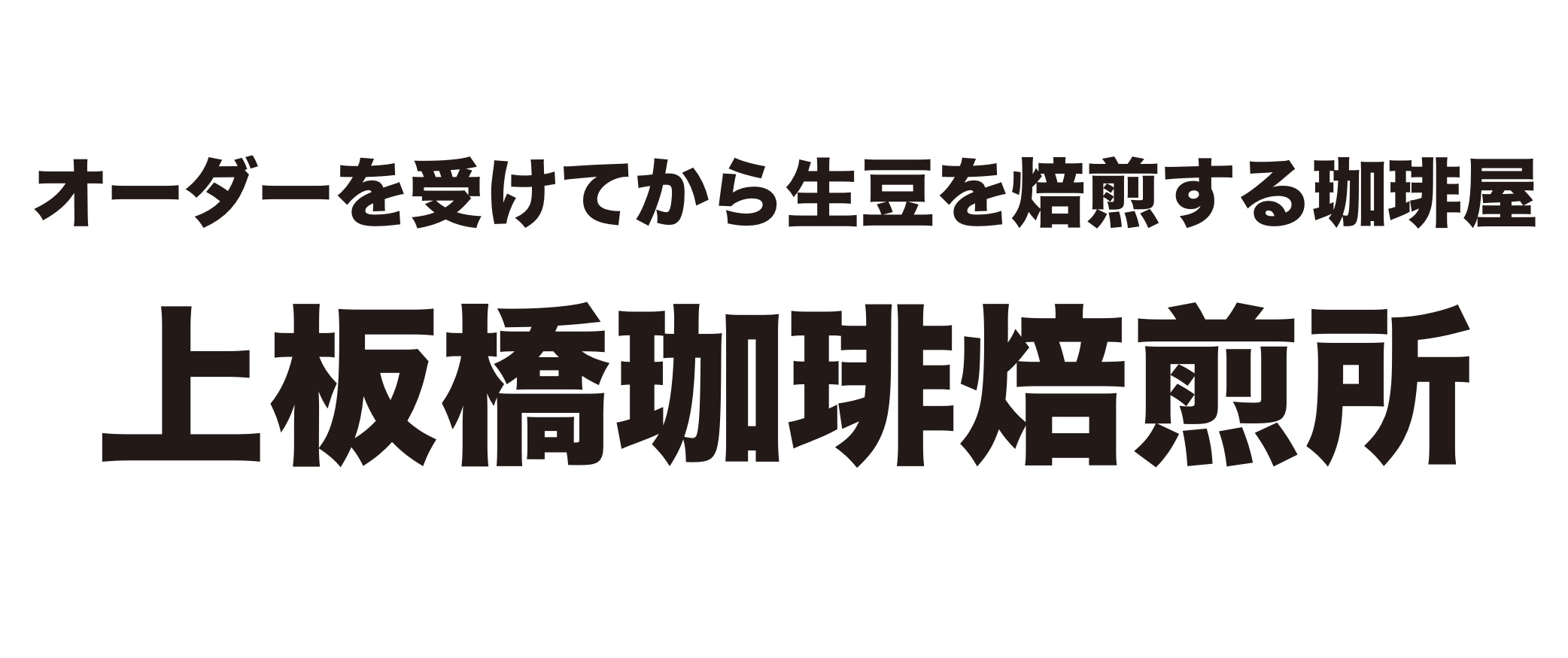コーヒー焙煎は奥が深くとても楽しいですね。
インターネットは便利なもので、過去の論文なんかも簡単にアクセスができるようになり、科学的な理解を深めるのに非常に良いツールとして機能してるかと思います。
ただ、何度も思い出したように調べ直すものめんどくさいので、自身の備忘録的な目的で、記述や知見をまとめてみました。
過去の論文なんかもあるので、実際はさらに新たな事実や知見があるかもしれませんので、何かお気づきの方や研究されてる方いらっしゃいましたら、お問い合わせからご意見やご教示頂ければと思います。
特に加水分解やカラメル化なんかは、奥深すぎて、いろんな方の所感も伺ってみたいですね。
では、軽く以下から記載していきます。
100℃ 水の沸点
これは水が蒸発する温度ですね。手鍋焙煎なんかをしている人は特にわかりやすいですが、水蒸気が発生している温度で、水抜きの温度帯とも言われています。ゆっくりと豆の中心まで火が通るように150℃付近まで温度を上げています。
150℃ メイラード反応
メイラード反応が起こる温度で、この温度から少しずつコーヒー豆の色の変化が起きてきます。お肉や野菜などでも焼けたいい香りはこのメイラード反応の効果です。
コーヒー豆ではタンパク質とショ糖によりメイラード反応が起きます。メイラード反応はコーヒーにコクを与えると言われています。
160℃ カラメル化
160℃〜180℃でカラメル化が起こると言われており、コーヒーの生豆は多糖類と少糖類と合わせて半数以上がコーヒー豆の成分で、大きく味に影響する成分だと個人的には思っています。カラメル化もコクや香りをもたらせてくれる要素ではないでしょうか。
多糖類は、加水分解をすることで、複数の単糖類に変化します。この加水分解後のカラメル化もより焙煎を複雑にしているのでしょうか。
ショ糖
いわゆる砂糖で甘みがあります。ショ糖のカラメル化は160℃です。
珈琲の甘みなんかはこのショ糖の影響なのでしょうか。
ただ、焙煎すると1%以下に減少することから、多糖類が加水分解し他の単糖類が生成されることによる影響もあるのでしょうか。
個人的にはショ糖のカラメル化によるコクと残存するショ糖によるコクが出るのではないかと考えています。
ガラクトマンナン
マンノースとガラクトースが結合したユニットから構成される多糖類です。
ガラクトマンナン160℃でガラクトースはカラメル化するようです、マンノース(カラメル化の温度を見つけることができず、構造的に似ているマルトースが180℃なのでその付近か?)。
セルロース
多糖類で加水分解で、グルコースが生成されます。グルコースのカラメル化は160℃となります。
ペクチン
複合多糖類で、細胞壁を接着する役割。ラムノース、キシロース、ガラクトース、アラビノース、グルコース等の糖が含まれる。全成分のカラメル化に関する記述は見つけられませんでした。
単糖類の特徴を見る限り、110℃から180℃の範囲でカラメル化するのではないかと考えています。
詳細わかる方いましたら問い合わせフォームからメッセージ頂ければ加筆致します。
165℃ 加水分解
この温度帯はクロロゲン酸がキナ酸とカフェ酸に加水分解される温度。
カフェ酸に関しては謎が多すぎて、より詳細に調べることが必要になりそうです。
キナ酸
高温で加熱することで、急激に含有量が減るようです。拝見した記述では焙煎して7分210℃に到達した時点から一気に半減していました。
時間経過によるなだらかな減少ではなく、一定温度からの急激な減少の為、温度が肝になると考えています。
微かな酸味が特徴のようで、焙煎深度が深いと酸味が消えるのは、このキナ酸の影響が大きいかと考えています。
カフェ酸
ある学術記によると、カフェ酸は不安定性に乏しく、クロロゲン酸量の減少に反比例してカフェ酸が増えることはなく、加水分解による生成と、加熱分解による消失が同時に起こっていることを示唆しているのではないかとのこと。
カフェ酸は時間と共に消失してしまうようで、カフェ酸を残すためには、加水分解が起きてからなるべく早めに焙煎を終える必要がありそうです。
ただ、カフェ酸はキリンの缶珈琲の研究の記述で、カフェ酸自体に味は無いが、缶珈琲の加温によりカフェ酸が缶コーヒーの味に変化をもたらすといった内容がありました。
再加熱時のネガティブな要素(取り除きたい要素、実際にカフェ酸だけを取り出すのは不可との結論で別の手段を選択)として記載があり、何かしらの影響を与えているようですが、加熱前に添加しても味に変化はないようで、高温度帯(お湯で抽出した際)での味への影響があるということでしょうか。
主に酸味が増すようです。
うーん、難しすぎる。
また、カフェ酸は170℃付近で脱炭酸反応が起き、p-ビニルカテコールという物質が一時的に生じ、重合していき、この物質が焙煎コーヒーの苦味に似ていおり、カフェインの苦味の20倍の強さがあるとの記述を見つけました。
つまり、浅煎り珈琲の苦味が控えめなのは、170℃以上の焙煎時間の長さにもある程度関与して来るのでしょうか。
180℃
このあたりから1ハゼが起きてくるイメージですが、低温焙煎なる手法の記事を見つけ、150℃程度でもハゼがくるようです。
ここまでの温度帯の成分に関して、酸味の要素はこの180℃から200℃(温度帯がアバウトですいません。)が酸味の有無を分けるターニングポイントになってくるのでしょうか。
まとめ
ここまで調べておいてあれなんですが、珈琲の味に酸味や複雑さなど個性を求める場合、180℃以上に加熱する意図や根拠は上記成分変化からはわかりませんでした。
高温にして焙煎することで、揮発性の成分が逃げないようにするというのが高温にする意図でしょうか。
ただ、個性を残すという部分に関して言えば、成分変化をしっかりと起こして、その成分を残存させるには150℃から180℃の間が非常に重要なのではないかと思いました。
珈琲研究の先駆者や現在も研究している方に敬意を示しつつ、一杯の珈琲を楽しめるようになると面白いですね!
最後までお読み頂きありがとうございます!
ブログの更新情報は、記事更新の瞬間にTwitterでも呟きますので、是非フォローをしてください!